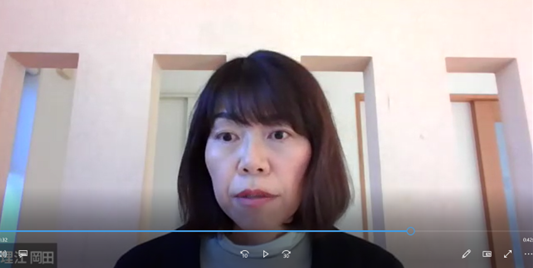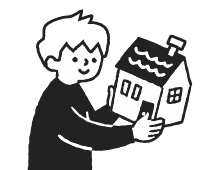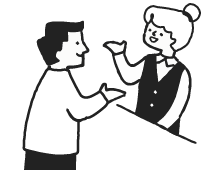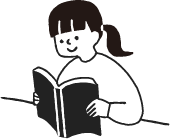静岡県日本語ボランティアセミナー2023(静岡県における地域日本語教育推進セミナー)
毎年、多文化共生社会における地域日本語教育について理解を深めることを目的とし、日本語教育に関わっている方や関心のある方を対象としてセミナーを開催しています。
今年度は1月21日(土)オンラインで静岡県多文化共生課と共催で実施しました。
あらためて考える、市民による地域日本語教育の可能性
講師:(一社)多文化社会専門職機構(TaSSK)菊池哲佳氏
講義は、現在の地域日本語教育がどのような背景と経緯で構築されてきたか、という流れを確認するところから始まりました。地域日本語教育はボランティアに支えられている現状ですが、年々日本語学習者は増加しており、その年齢、目的、日本語レベルは多様化しています。また、地域日本語教室は開催頻度が限られることや、多様化する学習ニーズへの対応等の課題がある中で、参加者同士が多様な文化に触れ、学び合い、安心して参加できる居場所であること、学習者が社会参加につながることばを獲得するための機会であることを確認しました。2019年には「日本語教育の推進に関する法律」が施行され、地域日本語教育は言語習得の側面から行政が責任をもって取り組むべき活動として明示されました。更に、昨年出された「地域における日本語教育の在り方について(報告)」では、地域日本語教育で目指す日本語レベルやそれに伴う学習時間数などが示されました。菊池氏からは、日本語の学習権を保障するまでの制度化には至っていないものの、今後はより一層、市民活動としての相互学習と施策として推進される言語習得の融合が重要になるのではないか、というお話がありました。また、市民と行政が対等な立場でビジョンや課題を共有して連携を深めるとともに、連携・ネットワークの中で人、情報、手段等の新たな社会資源を創出し、多文化共生を推進していくことが重要であると語られました。

静岡県地域日本語教育推進方針について
モデル日本語教室の報告(富士市、焼津市)
静岡県では令和2年度「静岡県地域日本語教育推進方針」に基づき、総括コーディネーターを配置したことや、行政が実施主体となるモデル日本語教室の開設、補助制度、教材の作成等に取り組んでいることの説明がありました。
令和4年度モデル日本語教室に取り組んだ富士市からは、開設に至った経緯と苦労した点などの報告がありました。会場付近からの学習者の参加が見られなかったことや日本語ゼロレベルへの対応等、課題はあるものの、全12回の教室終了時には、学習者からはまた参加したいとの声が多く、サポーター(日本語ボランティア)からは外国人市民への理解が深まったという感想が聞かれたという報告でした。
焼津市からは、外国人と日本人の接点が少ないという市民アンケート結果を背景とし、教室開設に至ったことや、募集時にはサポーターは99人、学習者は50人の申し込みがあったという報告がありました。また、日本語教室の動画を通して、サポーターも学習者も楽しそうに日本語教室に通い、主体的に参加している様子が紹介されました。日本語初期レベルの学習者への対応や、サポーターのレベルアップ等の課題を確認し、さらに外国人と日本人の交流機会を作っていくことで多文化共生社会への理解を進めていきたいという報告がなされました。
外国につながる高校生を対象とした日本語及び進路支援
発表者:NPO浜松日本語日本文化研究会 岡田理江氏
岡田氏からは静岡県立浜松北高校定時制で実施している日本語教室から見える課題についてお話いただきました。高校生は特に漢字を原因とし、授業参加に苦労していること、アルバイトを優先させる生活を送っている生徒が多いため、自主参加に任せられている日本語教室では、日本語学習への目的意識がないと出席率が低くなってしまうという課題が挙げられました。また、小中学校と違い、高校ではそれぞれが進路を具体的に決めなければならないが、何をどうしたらよいか、自分で決めることが出来ない生徒が多く、保護者も自国の経験しかないことから、同胞からの口コミ等に頼ってしまうというお話がありました。
これらの課題をふまえ、生徒がキャリアについて考えながら、年齢相応の知識や漢字力を強化することを目的とした日本語学習教材「オレンジドリル」が作成されたことが報告されました。