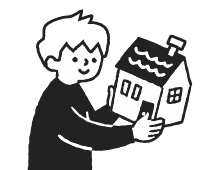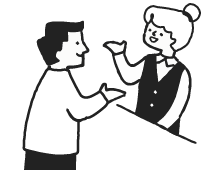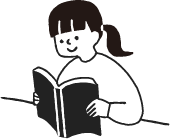令和6年度静岡県災害時外国語ボランティア研修会「外国人の声をきこう」(静岡県委託事業)

日本には防災訓練がありますが、「地震を体験したことがない」、「防災訓練に参加したことがない」という外国人がたくさんいます。研修会では、インドネシア、中国、ネパール出身の留学生や社会人から災害経験や母国との違いについてお話を聞き、外国人の防災意識や、日本で暮らしていて不安に思うことについて理解を深めました。
日時:令和6年11月9日(土)13:00~15:30
会場:静岡県地震防災センター(静岡市)
参加者:20名
発表者:柳(リュウ) 金函(キンカン) 氏(静岡県立大学修士1年)
Arief(アリフ) Maulana(マウラナ) 氏(㈱SBS情報システム勤務)
Naresh(ナレス) Maharjan(マハラジャン) 氏(ナマステ・ネパール静岡会長)
ゲスト:駐日ネパール大使:H.E Dr.Durga(ドゥルガ) Bahadur(バハドゥール) Subedi(スベディ) 氏

まず始めに、静岡県災害時外国語ボランティアの活動について静岡県多文化共生課河合さんから説明がありました。その後、中国出身の柳さん、インドネシア出身のアリフさん、ネパール出身のナレスさんから母国との災害の違いや、静岡県で災害を経験した際に感じたことなどについて発表をしていただきました。柳さんの出身地である中国の山東省では地震がなく、学校でも防災訓練はなかったそうです。静岡県に来て地震を経験した時は、自分自身の体調が悪くてめまいがしていると思ったこと、スマートフォンから流れる緊急地震速報のアラームに驚いたというお話をされました。インドネシア出身のアリフさんからも母国では防災訓練はないというお話しがあり、日本で地震を経験した際には何が起きたのか分からなくて神様にお祈りしたそうです。今は防災ラジオを購入し、地域の防災訓練にも積極的に参加し、災害時に備えているとのことでした。また、日頃から地域の農業ボランティアへ参加をするなど、地域との繋がりを大切にしているそうです。ネパール出身のナレスさんからは、母国には海はないけれど、地震は日本と同じようにとても多いというお話がありました。また、レンガ造りの建物が多いため避難時の落下物による被害が大きいそうです。ナレスさんはご自身のライフワークとして、ネパールに静岡県地震防災センターのような建物の建設を検討しているという発表がありました。

3人の発表者からは地域の避難訓練の案内や、緊急地震速報のアラームに「やさしい日本語」があれば、在住外国人にもっと伝わるのではないかという意見が聞かれました。また、本研修会にはスベディネパール駐日大使が参加され、静岡県が開発した防災アプリの広がりに期待しているというお話がありました。
グループ別意見交換では、災害時に普段から備えていることについて話し合いました。AFC国際学院に通う留学生も積極的に自分の考えを伝えました。

最後に、静岡県地震防災センターの体験プログラムに参加しました。ふじのくに防災シアターを鑑賞し、地震や津波の仕組みについて説明を受け、地震体験装置を体験しました。
参加者の皆さんからは、外国人側からの視点を知れて良かった、日頃から地域の人と関わりをもてるようになりたい、地震など災害に対してできる準備をしていきたいなどといった感想が聞かれました。