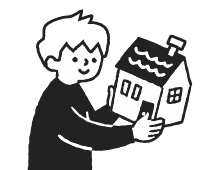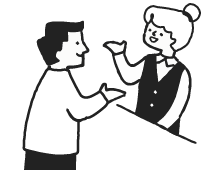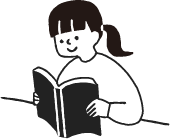令和5年度静岡県災害時外国語ボランティア研修会「オンライン通訳演習」
静岡県は、県内で大規模災害が発生した際に、外国人県民に寄り添い、多言語により通訳や翻訳の支援を行う「災害時外国語ボランティア」を育成しています。今回は3月2日(土)、3月3日(日)にオンラインで開催した、災害時外国語ボランティア研修会について報告します。
| 日時 | 参加者 | 講師 |
| 3月2日(土)9:30~12:00 英語 | 20名 | 岩田久美 氏 (スペイン語通訳者・講師 (一社)多文化社会専門職機構認定相談通訳) |
| 3月2日(土)13:30~16:00 中国語 | 6名 | |
| 3月3日(日) 13:30~16:00 ポルトガル語・スペイン語 | 16名 |


研修会は「オンライン通訳演習」と題して、英語、中国語、ポルトガル語・スペイン語の言語別に開催しました。講師は、多文化社会専門職機構認定相談通訳、また、外国人支援NPOの相談通訳などとして活動している、岩田久美氏に務めていただき、災害時外国語ボランティアの心構えや、通訳・翻訳における注意点等について学びました。講義では、通訳者に求められる訳出技法やマナー、言語的マイノリティを通訳・翻訳面で支援することによってホスト社会につなげる橋渡しになるコミュニティ通訳としての役割等について紹介していただきました。コミュニティ通訳は地域社会に暮らす外国人の生命や人生に大きく関わるため豊富な背景知識や技能が必要とされる、特に災害時には各専門領域の知識や経験が総合的に求められると説明がありました。やさしい日本語についても紹介があり、メモリーエクササイズ、リプロダクション、シャドーイングといった、自分で行える通訳の基本的な練習方法についても教えていただき、実際に練習を行いました。
後半はグループに分かれて、与えられたシナリオを基にロールプレイングを行いました。オンラインということで対面とは違う難しさもありましたが、皆様積極的に取り組んでいただきました。参加者からは、災害時特有の専門用語の訳し方が難しかった、災害時に良く使う単語は事前に把握しておいた方が良い、災害時に行政が提供する各種制度の知識もある程度知っておく必要があると思った、といった意見が聞かれ、文章の訳し方や疑問点等について活発な意見交換がありました。ネイティブの通訳者の方にも参加していただき、外国人は災害時どんなことに困るのか、専門用語を訳しただけでは背景知識を持たない人には伝わらないので、具体的な説明が必要になるといった意見がありました。通訳の練習だけでなく、外国語ボランティアに関心のある方同士が交流を深める良い機会とすることができました。
参加していただいた皆さまありがとうございました。
主催:静岡県(運営(公財)静岡県国際交流協会